山本 直彌
副社長執行役員
保有資格:宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/マンション管理士/管理業務主任者/マンション維持修繕技術者
大手マンション管理会社での業務経験6年、大手不動産仲介会社での業務経験9年、その他PM・BMマネジメント経験3年。マンション管理フロント業務として50棟以上(5,000戸以上)の管理業務実務、不動産仲介取引件数は累計500組以上。
こんにちは!らくだ不動産の山本です。
「最近よく耳にする『不動産エージェント』って、従来の不動産仲介と何が違うの?」
「不動産のことを相談したいけど、誰を頼ればいいかわからない…」
近年、不動産エージェントと名乗る会社が増え、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、不動産のプロが「不動産エージェント」の実態を徹底解説。従来の不動産仲介との根本的な違いから、あなたの利益を最大化してくれる信頼できるエージェントの見つけ方まで、具体的なポイントをお伝えします。
不動産エージェントは、不動産という「モノ」を仲介するのではなく、お客様という「ヒト」の代理人として、資産やライフステージ全体の最適化を目指します。そのため、不動産の売買は目的ではなく、あくまで手段の一つと捉えます。本記事では、売却や購入の前提から一緒に考える「カウンセリング」の重要性から、住まいの観点だけではない相続や投資といった幅広い相談内容、さらにはSNS時代の情報収集の注意点まで、不動産エージェントの全てを網羅的に解説します。
目次
このセクションでは、不動産エージェントと従来の不動産仲介の根本的な違いを3つのポイントで解説します。
まず、日本において「不動産エージェント」に法的な定義はありません。その上で、私たちが考える最も大きな違いは、サービスの対象が何かという点です。
不動産仲介:不動産という「モノ」を対象とし、その取引を成立させること(仲介)が仕事。
不動産エージェント:売主様や買主様という「ヒト」を対象とし、その方の代理人として不動産を含めた資産を最適且つ最大化することが仕事。
つまり、不動産仲介が物件に紐づくのに対し、不動産エージェントは依頼者に紐づくという根本的な違いがあります。
大前提となる考え方が違うため、ゴール設定も大きく異なります。
不動産仲介:不動産を売買・賃貸すること自体が「目的」でありゴールです。
不動産エージェント:売買や賃貸はあくまで「手段」の一つ。お客様の資産状況やライフプラン全体をより良いものにすることが最終的な「目的」です。
お客様の状況によっては、売らない・買わないという選択肢を提案することもエージェントの重要な役割です。
不動産エージェントはあくまで売主様、あるいは買主様、どちらか一方の「代理人」です。そのため、一人の担当者が売主と買主双方を担当する「両手取引」は、利益相反の観点から原則として行いません。
売主様のエージェントは、あくまで売主様の利益のために活動し、その取引における買主様には、別のエージェントがつくべきだと考えます。不動産エージェントを名乗っていても両手取引を積極的に行っている場合は、私たちが考えるエージェントの理念とは異なると言えるでしょう。
このセクションでは、不動産エージェントが具体的にどのようなアプローチでお客様をサポートするのかを解説します。
不動産エージェントの仕事は、病院の「問診」に似ています。まずはお客様が「なぜ売りたいのか」「なぜ買いたいのか」という根本的な目的や、現在の資産状況、家族構成、将来のライフプランまで、じっくりとヒアリングを行います。
「売る」「買う」ということを前提とせず、「そもそも本当に今、売る(買う)べきなのか?」という入り口から一緒に考えることが、本当の意味でお客様のためになると考えているからです。
カウンセリングの結果、お客様の目的を達成するためには、当初の考えとは異なる選択肢が最適だとわかるケースもあります。。
売却相談の例:売却をやめて賃貸に出す、リノベーションして活用する、税金や家族の成長を考慮して数年後に売却する、など。
購入相談の例:お客様の本当の予算や希望を深掘りし、「7,000万円でこのエリア」という当初の希望が、実は「6,500万円が上限で、もっと別のエリアが良い」という結論に変わることもあります。
このように、お客様が思いもよらなかった選択肢を提示し、売主様や買主様の利益を最大化できるのが、優れた不動産エージェントです。
複数の不動産をお持ちの方には、長期的な視点での売却戦略を立てることも可能です。
例えば、5軒の不動産を将来的にすべて手放したいというご相談の場合、一般的な仲介会社なら一括で売却することを提案しがちです。しかし、エージェントは市況や物件の特性を分析し、
価格下落リスクが高い物件から先に売る
賃借人がつきにくい物件から手放す
エリアの再開発計画に合わせて売却時期を調整する
といった戦略を立て、数年がかりでお客様の資産形成をサポートします。
このセクションでは、あなたにぴったりの不動産エージェントを見つけるための具体的なステップを紹介します。
最も重要なことは、物件から探し始めないことです。ポータルサイトで気になる物件を見つけて問い合わせると、その物件を扱う仲介会社の営業担当者がつき、メリットを中心に伝えられて、買う前提で話が進んでしまいがちです。
そうではなく、まずは「この人になら本音で相談できる」と思えるエージェント(人)を探すことから始めましょう。
良いエージェントかどうかを見極めるポイントは、初期のカウンセリングをどれだけ丁寧に行ってくれるかです。
すぐに物件を見に行くことを勧めるのではなく、まずは時間をかけてあなたの状況や想いをヒアリングしてくれるか。そして、あなたの考えの解像度を上げるための提案をしてくれるか。少しでも「本音で話しづらいな」と感じたら、別の人を探すのが賢明です。
エージェントを探す際は、会社のホームページをしっかり確認しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。
「パーソナリティ」を打ち出しているか:会社としてではなく、エージェント一人ひとりのプロフィールや得意分野(マンション、戸建て、収益物件など)、人柄がわかるページが充実しているか。
お客様の声や体験談が豊富か:実際に担当したエージェントへの口コミが掲載されているか。Googleマップの口コミなども参考になります。
お客様が売買に至らなかった場合でも、紹介や口コミで応援してもらえる関係性を築けているかは、そのエージェントの信頼性を測る一つの指標になります。
不動産売買だけじゃない!不動産エージェントへの相談範囲
不動産エージェントの専門性は、不動産売買に限りません。複雑な問題にも対応可能です。
相続は、権利関係が複雑になることもあり、不動産エージェントだけでは解決できない領域も含まれます。しかし、信頼できるエージェントは、司法書士・弁護士・税理士といった各専門家との強力なコネクションを持っています。
相談内容に応じて最適な専門家へつなぐ「ハブ機能」を果たせるかどうかが重要です。相続に不安を感じたら、まずは思い立ったタイミングで相談してみましょう。事前にシミュレーションを重ねておくことが、トラブル回避の鍵となります。
住宅だけではなく、オフィスビルや商業ビルの売買といった専門性の高い分野も相談可能です。
この分野に長けたエージェントは、独自のネットワークを駆使し、
独自ルートでの購入打診先の選定や
オフィスビルから住宅へのコンバージョン(用途変更)を提案する
など、多角的なアプローチで売却の成功を目指します。
YouTubeなどで情報発信している不動産関係者も増えていますが、注意点があります。それは、発信者が今も「実務」を行っているかどうかです。
不動産取引は一つとして同じものがなく、常に「応用」が求められます。評論家的な抽象論ではなく、自身の体験談やお客様との具体的な事例を語れるかどうかが、現場の引き出しの多さ、つまり本当の実力を見極めるポイントになります。発信者と実務者がイコールであることが理想です。
今回は、不動産エージェントの実態について詳しく解説しました。
最も重要なメッセージは、「不動産エージェントは、単なる不動産仲介営業職ではなく、あなたの資産と人生の目的達成に寄り添うパートナーである」ということです。
不動産に関する漠然とした不安やお悩みがあれば、まずは気軽に相談できて信頼のおけるエージェントを探すことから始めてみてはいかがでしょうか。
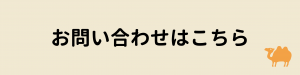
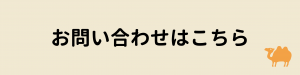
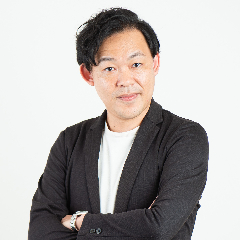
副社長執行役員
保有資格:宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/マンション管理士/管理業務主任者/マンション維持修繕技術者
大手マンション管理会社での業務経験6年、大手不動産仲介会社での業務経験9年、その他PM・BMマネジメント経験3年。マンション管理フロント業務として50棟以上(5,000戸以上)の管理業務実務、不動産仲介取引件数は累計500組以上。
希望エージェントの空き状況を
確認したい場合は050-1745-5799まで
お電話下さいませ。
※10:00-17:00(定休日:火・水)